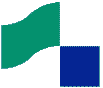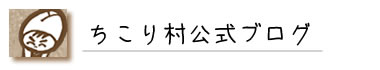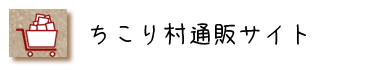文化庁長官表彰受賞 フリーフライデー 中山道広重美術館 広重と版元(浮世絵出版社)
文化庁長官表彰受賞 フリーフライデー
中山道広重美術館
広重と版元(浮世絵出版社)

中山道広重美術館学芸係長
常包(つねかね) 美穂さん
筑波大学大学院人間総合科学研究科博士前期課程修了後、2022年より現職。専門は日本近世絵画史。
※背景は中津川(雨)
◆広重と版元
―現在、大河ドラマでも浮世絵の版元・プロデューサー的存在が注目されています。歌川広重と版元の関係についてお聞きかせください。
常包さん 歌川広重(1797~1858)は、20代~60代の間に、何人かの版元と関わっています。デビュー当初は美人画が中心でしたが、30代の頃に風景画を描き始めます。二点透視図法や物を斜めから見た構図で、人が日常に目にするものに近いのが特徴です。最初に大判の風景画「東都名所(通称、一幽斎がき)」(1831頃)を手掛けた版元は、川口屋正蔵です。その後佐野屋喜兵衛も江戸名所を出版しています。広重の出世作と言える「東海道五拾三次」(1833頃)を手掛けたのは竹内孫八です。大規模なシリーズものを企画するのは、蔦屋重三郎のように何代も続く、今で言ったら会社組織の大手版元が主流でしたが、孫八はもともと質屋が本業でした。自身も絵を嗜んでいたものの、一代限りでおしまいとなった小さな版元です。広重晩年の代表作と言える118枚のシリーズ「名所江戸百景」(1856~58)は、魚屋栄吉です。
◆版元の変遷と広重
―版元が変わっていったのには、理由があるのですか?
常包さん 人間なので単純にけんかをしたとか、合わなくなったという事もあるかもしれませんが、版元にも流行り廃りがありました。複数の版元から声が掛かるという事は、それだけ人気があった証でもあります。また版元には版権があり、同じ主題の出版物が競合しないよう権利の制約もありました。
―利益の占有のような現代にも通じるものがあったのですね。
常包さん 広重自身も初期の臨場感を重視した作風から、一歩引いた客観的な視点に変わっています。これは40代の頃、広重自身が旅に出たことにより、風景の見え方が変わったのだと推察できます。また、初期は藍色薄墨の水墨画のような画が特色でしたが、「名所江戸百景」の頃には、色鮮やかさが加わっています。少ない色数で表現できたのは、空白さえも味方にする調和のとれた構図にありました。その一歩引いた客観的な視点が、穏やかで品がある印象を与えるのだと思います。浮世絵とは、自分一人で完成するわけでなく、原画があり、版木を彫る人、版木に色を付けて摺る人がいて完成するものだとよく理解していて、それぞれの工程に信頼を置き、分業の先の完成図が見えていたのでしょうね。天保の改革(1841~43)では、風俗の悪い絵を描かないように、1枚16文まで、摺りは8色までなどの規制がされましたが、広重はもともと風景画でしたし、工程も最小限でコストも抑えられていたので、とがめられることはなかったようです。また、空間にぼかしの技術を取り入れることで、摺りの技術向上にも一役買っていました。
―広重自身、時世や流行に敏感なプロデューサー的な感覚をもった人だったのかもしれませんね。(終)
(株)サラダコスモ・ちこり村がスポンサー協力
フリーフライデーの活動が文化庁
長官表彰を受賞しました!
毎週金曜日は
中山道広重美術館の入館料は無料です。
文化庁長官表彰&春季特別企画展の詳細は⇓