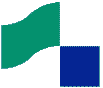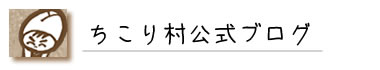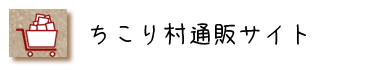「なかつがわ今昔物語」Vol.1 中山道中津川宿
江戸から数えて45番目 今に残る宿場の風情
中津川市も外国からのお客さまが増えています。来訪される多くのみなさんが中山道を歩きます。「中津川宿」はその宿場ゾーン。市街地の中心にあり、位置と道筋は昔と変わりません。江戸時代の建物も残っています。
中津川宿は江戸・日本橋から数えて45番目の宿場で、中山道の全69宿の中でも大きな部類でした。東から現在の地名で、淀川町、新町、本町と続き、長さは1・2km。落ち着いた色調に舗装され、歩きやすくなっています。
往時はどうだったのでしょう。
江戸後期、寛政年間(1789~1801年)のころの規模は、家屋175軒、人口1230人。中心は本町でした。幕府の役人や諸大名など身分の高い人が泊まる「本陣」と「脇本陣」、さらに旅籠(はたご)、問屋、茶屋、馬屋……様々な店が並び、家々も連なっていました。
本陣はどんな建物だったのでしょうか。
入り口は5軒続きの長屋式。中央の1軒分が門になっていたそうです。お屋敷の中は「玄関の間」「三の間」「次の間」「中の間」「上段の間」と続き、上段の間には湯殿(風呂)もあり、現代の感覚からはびっくりの格式です。現在、本陣はなく、残っているのは土蔵など脇本陣のごく一部です。
本町は2カ所で道が直角に折れ曲がっています。宿場特有の「枡形(ますがた)」です。視界をさえぎり、有事の際に一気に攻め込まれないための工夫です。さらに旧家の特徴には「卯建(うだつ)」があります。側面を主屋根より高くし、別の小さな屋根を載せて格式と防火の機能を演出しています。
中津川宿には人と物が行き来し、この地の政治や文化にも影響を与えました。21世紀の今は瀟洒(しょうしゃ)なゲストハウスもあります。現代の旅籠です。みなさんも歩いてみて、歴史に思いをはせてはいかがでしょうか。

「卯建」と「枡形」が見られ、中津川宿らしい一角。外国人の来訪も多くなっています=中津川市本町

中津川宿の常夜灯=中津川市本町
この記事が一番古い記事です。
「一斎先生こんにちは」Vol.1 岩村町と佐藤一斎 >
>