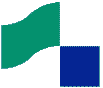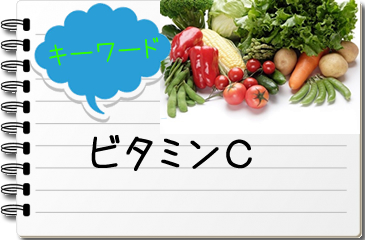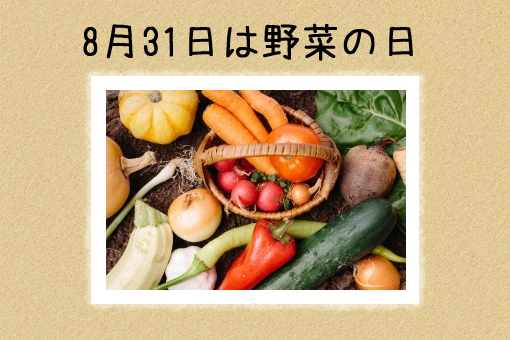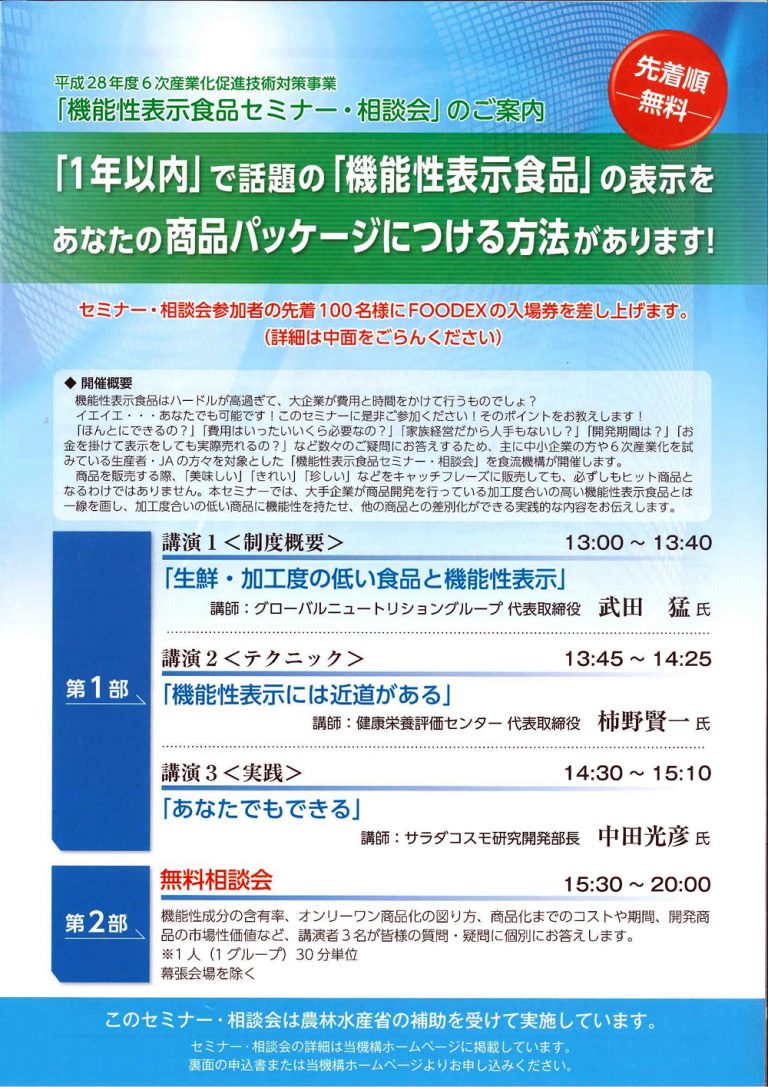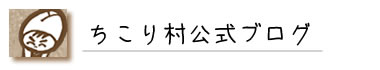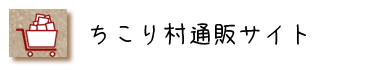ちゃんと知りたい!① 機能性表示食品とは?
 機能性表示とは?
機能性表示とは?
2015年の春から第三の機能性表示制度が始まります。
今までは、特定健康食品(いわゆるトクホ)と栄養機能食品にのみ許されていた機能表示が
新たな制度では、それ以外の食品、例えば農産物や生鮮食品にも
「安全性」や「機能性」について一定の条件をクリアすれば
企業や生産者の責任で「体のどの部分に良いのか」「どう機能するのか」が表示できるようになりました。
消費者庁が定めた基準に沿っているかどうかの「届け出型」です。

 機能性表示食品とは?
機能性表示食品とは?
「安全性」や「機能性」について一定の条件をクリアし、
「体のどの部分に良いのか」「どう機能するのか」が表示することが出来るようになった「食品」のことです。
一定の条件というのは?
![]() その食品(例えばトマト)を使った臨床試験に基づくもの。
その食品(例えばトマト)を使った臨床試験に基づくもの。
![]() その食品(例えばトマト)を使った既存の研究があるもの。
その食品(例えばトマト)を使った既存の研究があるもの。
![]() その成分(例えばトマトに含まれるリコピン)そのものの研究文献を集めて
その成分(例えばトマトに含まれるリコピン)そのものの研究文献を集めて
総合的評価に基づくもの。
以上の条件のうちひとつ当てはまれば機能性表示食品の根拠として認められます。
![]() ~
~![]() のどの条件に当てはまるものなのかは、
のどの条件に当てはまるものなのかは、
機能性表示食品のパッケージ記載されている
消費者庁から付与された届出番号から検索できるようになっています。
機能性表示食品は、審査は不要の「届け出型」です。
その食品についての安全性や機能性を示す根拠を
販売元(生産元)のサイトで発売の60日前までに公表することが
義務付けられているので、
消費者自身の目でその根拠を確認することが必要となってきます。

治療から予防へ。「トマトが赤くなると、医者が青くなる」![]()
病気になってから治す「治療」ではなく、日頃からの生活習慣を改善することによって、
病気を「予防」する。
その中心となるのが「食生活」です。
「トマトが赤くなると、医者が青くなる」そんなことわざが昔からありますが、
なぜ、トマトは健康に良いのか?
それは、トマトには、リコピンが多く含まれており
リコピンには、血管の働きをサポートする機能があるからです。
そう言った機能性が表示されるようになれば
私たち消費者自身が、自分の目的にあった食品を選ぶことができるようになり
「治療」から「予防」に向けて生活を改善していくことができます。
機能性食品は薬ではないということを理解したうえで
自分には何が必要で、そのために何を選択するか、
取り過ぎないなどの量の加減などを判断する必要があります。
また、機能性食品はその根拠を消費者自身の目で確認する必要があるため
今まで以上に、情報選択の’目’と「予防」への意識と知識が必要になってきます。
【機能性表示食品】【ちゃんと知りたい!】
この記事が一番古い記事です。
ちゃんと知りたい!② 栄養機能食品 >
>